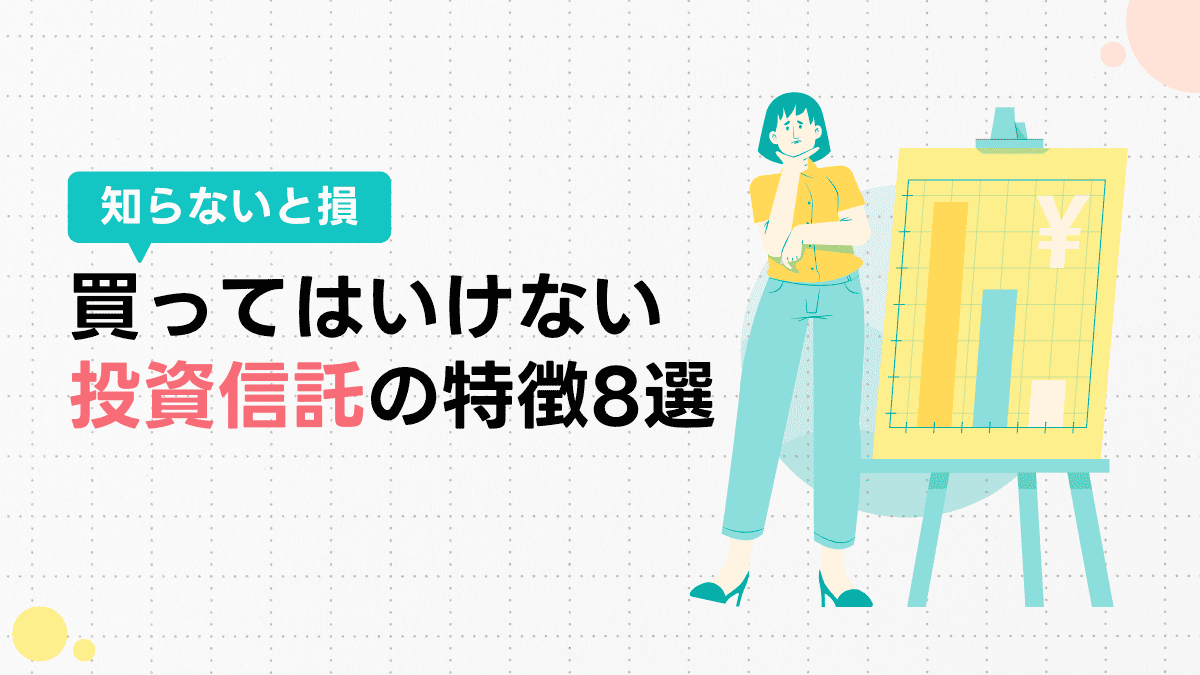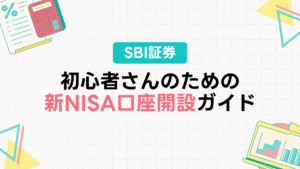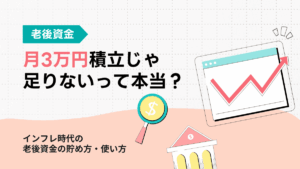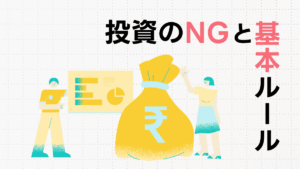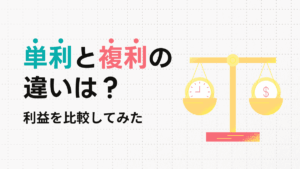少しでも将来のためにお金を増やしたい
子どもの教育費や老後資金も気になる…
そんなとき、お金を増やす手段として投資は欠かせません。
なかでも投資信託は、投資初心者でも始めやすくて人気。
でも実は、投資信託の中には「買ったら損する」「全然お金が増えない」そんな商品もたくさんあるんです。
だからこそ、「どれを選ぶか」が本当に大事。間違ったものを選ぶと、大切な家計のお金が増えないばかりか、むしろ減ってしまうかも…。
そうならないためにも、今回は「買ってはいけない投資信託の特徴8選」をわかりやすくお伝えします。
家計を守りつつ、賢く増やすための参考にしてくださいね。
① 銀行や証券会社の窓口で勧められたファンド
金融機関は「あなたの資産形成」より「自社の儲け」が最優先
銀行や証券会社の窓口で投資信託を相談すると、「お客様に合ったものをご提案します」と、いかにも親身なふうに勧められますよね。
でも実は、その裏には「販売ノルマ」や「会社の利益重視の方針」が…。
窓口の担当者が勧める商品は、多くの場合
- 手数料が高い(購入時手数料が3%以上、信託報酬が1%超など)
- 儲かるかどうかは関係なく、売れ筋・ノルマ商品
になっていることが多いんです。
なぜなら、金融機関は「売った時に入る手数料(販売手数料)」が利益の柱だから。
あなたがその投資信託で儲かろうが損しようが、金融機関には関係ありません。
むしろ、手数料の安い投資信託(インデックスファンドなど)ばかり売っていたら、会社の利益が減るので担当者は評価されないのです。
窓口で買うと起きがちなリスク
- 購入時に数%の手数料を払わされる
→100万円投資したら、いきなり3万円マイナスからのスタート、ということも。 - 信託報酬も割高(年1%以上など)
→手数料だけで資産の増え方が鈍る。 - 毎月分配型やテーマ型など、流行っているが長期的には不利な商品が勧められやすい。
さらに、金融機関によっては「手数料の高いファンドを契約するとポイントが多くつきます」「キャンペーン中でお得です」などと、販売を後押しするトークが多用されますが、冷静に考えると「あなたの資産が増えるかどうか」ではなく「売る側が得するだけ」なんですよね。
ネット証券なら同じファンドでも圧倒的に安い
例えば、銀行の窓口で買うと購入時手数料3%、信託報酬1.5%のファンドが、ネット証券では購入時手数料0%、信託報酬0.1%の類似ファンドがあることは珍しくありません。
さらに、ネット証券なら自分で検索して
- 手数料の安いインデックスファンド
- 長期的に実績のあるファンド
を冷静に比較・選択できます。
窓口で買わない対策
- 投資信託はネット証券(SBI証券・楽天証券・マネックス証券など)で購入する
- 証券会社・銀行の窓口や電話営業には絶対に即答しない
- 勧められた商品は必ずその場で契約せず、家で一度ネットで比較・調べる
「いい商品は自分で探す」のが投資信託選びの基本です。
② 手数料が高すぎるファンド
手数料が「資産の伸び」をじわじわ削る
投資信託には、3種類の手数料がかかります。
| タイミング | 手数料の種類 | 説明 |
|---|---|---|
| 購入時 | 購入時手数料 | 買った瞬間に引かれる。最大3.3%が多い |
| 保有中 | 信託報酬 | 持っている間ずっと引かれる「年率の手数料」 |
| 売却時 | 信託財産留保額 | 売る時に引かれる場合がある |
特に重要なのが「信託報酬」
この中でも特に気をつけたいのが、「信託報酬」。運用中ずっと毎日コツコツ引かれ続けるコストです。
例えば100万円を年5%で運用した場合、
- 信託報酬0.1%:ほぼ5%の成長↗️
- 信託報酬1.5%:実質3.5%しか増えない💦
信託報酬で利益を削られると複利の効果が薄れるため、わずかな差に見えても長期で投資すると大きな違いになります。
実際、年1%の信託報酬差は20年後には数十万円〜数百万円の差まで膨らみます
手数料の目安
だから、投資信託を選ぶときは「できるだけ安い手数料のファンド」を選ぶのが大事です!
インデックスファンドの目安はこんな感じ。
- 購入時手数料なし
- 信託報酬0.3%以下
- 信託財産留保額基本的になし、あっても0.1%程度まで
ネット証券のファンドページで「手数料」「信託報酬」の欄を必ず確認しましょう
同じ指数に連動するファンドがいくつかある場合は、買う前に比較して安いものを選んでくださいね。
手数料が高いファンドの例
アクティブファンドは、年1%〜2%以上の信託報酬がかかることが多いです。
でも過去のデータを見ると、アクティブファンドの約8割が、低コストなインデックスファンドよりも利益が少なかったという結果。
高い手数料を払わされるのに、安いファンドより増えないんです…!
また、金融機関の窓口や営業電話で勧められる投資信託は購入時手数料3%、信託報酬1.5%〜2%など、とにかくコストが重いです。
ネット証券で手数料0%台の商品がたくさんあるのに、対面で何倍も高いファンドを買う必要はありません。
手数料が安いほど資産が増える
投資信託のコストは目に見えにくい出費ですが、確実にあなたの将来資産を削っていきます。
買う前にどれくらいコストがかかるのか必ず確認・比較して、できるだけ安いファンドを選びましょう。
③ 毎月分配型のファンド
「毎月お金が入る」「配当があるから安心」——そう思って買ってしまいがちなのが毎月分配型のファンド。
でも、投資初心者は避けたほうがいいです。
どうして危険なの?
実は、分配金は2種類あります。
- 運用益が出たときだけその一部を分配金として出す「普通分配金」
- 元本を取り崩して出す「特別分配金」
普通分配金は、運用でちゃんと儲かった分から出している配当です。
利益の一部を取り崩すので資産全体の目減りは少ないものの、再投資ができないので複利効果は落ち、資産が増えにくいデメリットがあります。
注意しなければいけないのは「特別分配金」。
これ、運用がうまくいってなくても定期的に分配金を出さなければいけないので、自分が預けたお金(元本)を崩して戻しているんです。
元本を取り崩す=ファンドの基準価格(値段)は減少し続けます。
見かけ上は「毎月お金が入ってくる」んですが、実はトータルの資産は目減りしていることも。
将来の運用益も減り、投資効率が極めて悪いので避けるべき、というわけです。
税金のデメリット
分配金は、もらうたびに約20%の税金が引かれるということをご存知でしょうか。
手取りの利益が減ってしまうのはもちろん、配当(分配金)を受け取るたびに税金ぶんの資産が減るため、運用効率が大きく低下します。
NISA口座なら利益に税金はかからないんじゃないの?
確かにNISAなら税金はかからないけど、分配金が出るたびに運用資産が減り、結局資産がなかなか増えない・減っていくという構造は同じです
「分配金がある=得」ではない!
毎月お小遣いのようにもらえる一方で、老後や将来のためにお金を増やしたい人には分配型の投資信託は不向き。
せっかく投資したお金が勝手に取り崩されていくので、思ったより増えないまま終わってしまうリスクが高いです。
大事なのは、分配金の有無ではなく資産全体が増えているかどうかを見ること。
長期で資産形成したいなら「分配金なし(再投資型)」のファンドを選びましょう。
運用して増えた分はファンドの中で再投資してくれるため、効率よくお金が増えていきます。
④ 流行りのテーマ型ファンド
テーマ型ファンドとは、特定の話題や業界に絞って投資する商品のこと。
最近だと以下のような「流行ワード」に飛びついたファンドが次々と登場しています。
- 生成AI
- 電気自動車(EV)
- 半導体
- クリーンエネルギー
- メタバース
「これから伸びそう!」と感じますが、実は危険な落とし穴がいくつもあるのです。
選ぶと危険な理由
- ファンドの設定時点で「すでに株価が上がった後」
- 流行はいつか終わる
- 中身をよく見ると微妙なことも
- 手数料が高いことが多い
テーマ型ファンドは話題になった後に設定されることがほとんど。
すでに多くの投資家が買って株価が上がりきった後に、投資信託が登場するというタイミングの悪さがあります。つまり、高値づかみになるリスクが高いんです。
また、テーマというのは流行り廃りがあります。一時的に話題でも数年後には別のテーマに取って代わられたり、成長が鈍化するリスクも。
結果として、パフォーマンスが急に悪化することも考えられるでしょう。
そして、テーマ型ファンドの中身(投資先の企業)を見てみると、実際にはそのテーマと直接関係ない会社や古くからある一般的な企業が組み込まれているというケースも多いです。
名前やイメージだけで投資させる商品も少なくないので、「はて、テーマ型とは…?」となりかねません。
テーマ型ファンドは、信託報酬などの手数料が高めという点も要注意。
コスト負担がかさみ、長期的なリターンは伸びにくい傾向があります。
興味があるなら「サテライト投資」で
こうした不安定なテーマ型ファンドは、値動きも激しく予測が難しいため「ギャンブル性」が高いです。
でも「どうしてもAIや半導体に投資したい!」という場合は、資産の一部(全体の5〜10%程度)だけで挑戦する「サテライト投資」にとどめましょう。
メインの投資は低コストの優良インデックスファンドにして、安定性重視で運用してくださいね。
⑤ 純資産総額が少ない・減っているファンド
ファンドの規模を表す「純資産総額」が少ないファンドにも注意。
純資産総額が大きい=そのファンドにお金が集まっている=人気ということを意味します
純資産総額が少ないと何が問題?
運用の効率が悪くなる
投資信託は投資家から集めたお金をまとめて運用するしくみです。集まったお金が多いほど幅広い企業や資産に投資できるため、効率よく分散投資できます。
投資先を分散しておくと、もしどこかの企業や国が不調になっても他の投資先がカバーしてくれるため、長期的に安定した成長が期待できます。
でも、集まったお金が少ない(純資産総額が少ない)と、たくさんの企業や資産に分散投資することが難しくなります。
その結果、投資先が偏ってしまい、もし一部の株や資産が下がった場合、ファンド全体の成績も一気に悪化するリスクが高まってしまうんです。
コストが割高になりやすい
ファンドを運用するには、会社の人件費やシステム管理などの固定コストがかかります。
お金が集まっていないと、1人1人の投資家が負担するコストが割高になり、ファンドの運用成績(リターン)が伸びにくくなってしまいます。
途中で運用が終了する(繰上げ償還)リスクが高まる
人気がなくお金が集まらないファンドは、途中で運用を打ち切られ、途中で運用を終了することがあります。
これを「繰上げ償還」といいます
繰上げ償還になると、まだ利益が出ていなくても強制的に解約されてしまい、予定していた長期運用ができなくなります。
さらに注意すべきなのが「純資産総額の推移」
規模が小さいだけでなく、「減り続けている」ファンドも危険です。
純資産総額が減る原因は、以下の2つ。
- ファンドの成績が悪く、評価額が下がった
- 投資家が売却してしまい、お金が流出している
どちらにしても、「人気がない」「見限られている」証拠です。
目安は「500億円以上」
ファンドの規模を見るときの目安は、「純資産総額500億円以上」です。
500億円未満のファンドは規模が小さいため、運用効率や安定性の面で注意が必要になります。できれば1000億円以上の規模があるとより安心です。
ただし、投資対象がマイナーな市場だったりめずらしいテーマの場合は、もともと小規模になりやすいため、一概にダメとは言えません。
それでも、原則としては「規模が大きいファンドの方が安定していて安心」と覚えておくとよいでしょう。
ファンドの純資産総額は、証券会社のファンド詳細ページや運用会社の公式サイトで確認できます。
「純資産総額の推移グラフ」を見られるサイトもあるので、右肩上がりに増えているか、減ってきているのかを見ることで人気や安全性の判断材料にすることができます。
⑥ 新しく設定されたばかりのファンド
投資信託にはすでに約6000本もの種類がありますが、実は毎月のように新しいファンドが登場しています。
でも、新しく設定されたばかりのファンドは要注意。慎重に見極めないと思わぬ落とし穴があります。
新規設定ファンドは「証券会社に都合がいい商品」
証券会社にとって、新しいファンドは話題性がありとても売りやすい商品です。
私たちも「最新」「今が旬」なんて言われると、つい気になりますよね。
でも実は、中身は既存のファンドとほとんど変わらなかったり、むしろ劣っている場合も…。
初心者は特に「新しい=これから成長する!」と感じがちなので、証券会社はその心理をうまく突いてきます。
過去の運用実績がないため実力がわからない
新規ファンドの最大の問題は「実績がない」こと。
過去のデータをもとに「もしこの方法で運用してたら、こんなに増えましたよ!」とアピールしてきますが、これって結局シミュレーションです。
実際の市場は予想外のことが起きますし、運用者の腕次第で結果は大きく変わります。
特にアクティブ型やテーマ型のファンドは、プロの判断力が超重要なので、数年運用してみないと「本当に強いファンド」かはわからないんです。
目安は「運用実績3〜5年以上」
多くの場合、すでに似た内容のファンドが存在します。新規設定ファンドやテーマ型ファンドはリスクが高いので、初心者がわざわざ選ぶ理由はありません。
ファンドを選ぶときは、最低でも3〜5年以上の運用実績があるものを選びましょう。
もしどうしても挑戦したい場合は、資産の一部(サテライト投資)にとどめ、本命の資産運用は実績のある王道ファンドを選ぶのが堅実です。
⑦ 複雑すぎるファンド
投資信託の中には、「4階建て構造」「デリバティブ」「オプション戦略」など、一見カッコよさそうな言葉が並んでいる商品があります。
でも、聞いてもよくわからない商品に手を出すのは絶対NGです。
自分で説明できないしくみは、リスクも見えない
投資の世界では、「自分が理解できないものには投資しない」が大原則。
なぜなら、仕組みが複雑だとどんなリスクがあるのか・どういう時に損するのかがわからないからです。
たとえば、「4階建ての仕組み」のファンドは、
1階:株式投資
2階:為替取引
3階:オプションの活用
4階:金利取引
…のように、いくつもの金融商品を組み合わせています。
この時点で、「なんだかすごそう」「プロに任せたら儲かるかも」と思うかもしれませんが、実際はその分手数料が高かったり、複雑な仕組みで損が膨らみやすい場合も多いんです。
手数料や中身が不透明な商品も多い
複雑なファンドほど、
- どこにどれだけ投資しているか
- どんなリスクを抱えているか
- どんな手数料がかかるのか
が見えにくいです。
「気づいたら運用成績が全然伸びてない」「手数料ばかり引かれていた」なんてことも…。
シンプルが最強
結局のところ、投資で成功している人たちが選んでいるのは、インデックスファンドのようなわかりやすい・シンプルな投資です。
「何に投資しているか」「どれだけ手数料がかかるか」がシンプルに説明できるものを選ぶ。これが、長期的に資産を守りながら増やすための最善策です。
わからないものには近づかない。シンプルこそが最強。
この考え方を、ぜひ覚えておいてくださいね。
⑧ アクティブ型の債券ファンド・レバレッジ付き債券ファンド
債券は、株式よりも値動きが穏やかでリスクが低いとされています。
そのため、「安定的にお金を増やしたい」「元本割れしにくい投資がしたい」と思って債券ファンドを選ぶ方も多いでしょう。
でも、ここにも「手を出してはいけないファンド」があります。
それが、
- アクティブ型の債券ファンド
- レバレッジ付き債券ファンド
です。
アクティブ型債券ファンドは手数料が高すぎる
アクティブ型とは「プロが銘柄を選んで運用するタイプ」のファンドのこと。
「プロが選ぶなら安心!」と思いがちですが、債券の場合はそこまでの差がつきにくいのが現実です。
しかも、アクティブ型は信託報酬(保有中にかかる手数料)が高めに設定されていることが多く、年1.5%を超えるものも珍しくありません。
それに対して、債券の期待リターンはもともと年数%程度。そこから1.5%も手数料を取られたら、せっかくのリターンがほとんど消えてしまうわけです。
レバレッジ付き債券ファンドはリスクの割にリターンがしょぼい
「レバレッジ付き」とは、資金を“てこ入れ”して運用額を増やし、値動きを何倍にも大きくするしくみ。
一見、「債券なのに大きく儲かるかも?」と思いそうですが、実際はそう甘くありません。
- 債券はもともと値動きが小さいため、レバレッジをかけてもリターンは知れている
- 一方で、損失が出たときのダメージは大きい
つまり、リスクばかり高まって、得られるリターンはしょぼいのが実態なのです。
債券に投資したいなら…
債券に投資したいなら、インデックス型の債券ファンドや個別の債券(国債・社債など)を選びましょう。
インデックス型なら手数料も低く、個別債券なら満期まで持てば元本と利息が確定する安心感もあります。
「債券は地味でコツコツ」のスタンスが基本。
わざわざリスクの高いアクティブ型やレバレッジ型を選ぶ必要はありません。
結論:買ってよいファンドの条件
投資初心者は「低コストのインデックスファンド」一択と言っても過言ではありません。
インデックスファンドとは、「市場全体の動きに連動することを目指すファンド」のこと。
市場平均に投資することで着実に資産を育てることができるのが特徴です。
インデックスファンドが初心者に最適な理由
インデックスファンドが初心者にピッタリな理由はとってもシンプル。
- プロの運用を任せなくても、市場平均を目指すだけだから安定性がある
- いろんな会社に自動的に分散投資されるから、リスクも自然に抑えられる
- 長期的に右肩上がりの成長が期待できる
特に初心者は「どの銘柄が伸びるか」を予測するのが難しいため、最初から市場全体に投資するインデックスファンドからはじめるのが安心です。
選ぶ基準
インデックスファンドの合格ラインは以下のとおり。
- 信託報酬0.3%以下
- 純資産総額500億円以上
- 運用実績3年以上
- 初心者でも内容が説明できるくらいシンプル
信託報酬0.3%以下
信託報酬は保有中にかかる手数料。
低コストでないと、リターンが目減りします。
最近では0.1%未満の超低コストな商品もあるので、0.3%以下を目安に選びましょう。
純資産総額500億円以上
ファンドの規模が小さいと運用が不安定になりやすく、コストも割高に。
500億円以上なら規模も安定し、繰上げ償還(途中終了)のリスクも低減します。
できれば1000億円以上あればさらに安心です。
運用実績3年以上
最低でも3年以上の運用実績があるファンドは、市場の変動に耐えた信頼性の証。
新しいファンドはリスクが高いため、実績のあるものを選びましょう。
初心者でも内容が説明できるくらいシンプル
「どこに投資しているのか」「なぜ選んだのか」を自分の言葉で説明できるかが重要。
仕組みが複雑だったり、よくわからないまま買ってしまうと、何かあった時に正しい判断ができなくなります。
投資は「わかるもの」に投資するのが鉄則です。
おすすめファンド
実際に多くの人が選んでいる投資信託がこの2つ。
- 全世界株式(オール・カントリー)
- 米国株式(S&P500)
どちらも「eMAXIS Slim」シリーズという、手数料が非常に安くて人気のある商品があります。
① 全世界株式(オールカントリー)
通称「オルカン」と呼ばれ、アメリカ・日本・ヨーロッパ・新興国など、世界中の約3000社にまるっと投資できるのが魅力。
過去30年で年平均9.9%成長した実績を持ち、長く持つほど右肩上がりが期待できる安心感があります。
しかも、世界の人口は2100年まで増え続けるという予測があり、これからも世界経済の発展とともに成長が期待できます。
おすすめ商品
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
- 信託報酬は年0.1%未満で非常に低コスト
- 中身の約60%はアメリカ株、次いで日本、イギリスなど
オルカンについては、以下の記事でくわしく解説しています。
② 米国株式(S&P500)
オルカン(全世界株式)よりも高いパフォーマンスを期待するなら米国株がおすすめ。
アメリカを代表する500社にまとめて投資する「S&P500」が人気です。過去30年間の年平均リターンはなんと12.5%。
500社の中には、Apple・Microsoft・Google・Amazon・Metaなど、世界的なハイテク企業がずらりと並んでいます。
アメリカは先進国の中でも数少ない「人口が増え続けている国」で、これからも経済成長が見込まれているのが大きな強みです。
おすすめ商品
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 信託報酬もこちらも年0.1%未満
- 上位銘柄はApple、NVIDIA、Amazon、Meta(旧Facebook)など
S&P500については、以下の記事でくわしく解説しています。
まとめ:買ってはいけない投資信託の特徴
今回は「買ってはいけない投資信託」について見てきました。
- 銀行や証券会社の窓口で勧められたファンド
- 手数料が高すぎるファンド
- 毎月分配型のファンド
- 流行りのテーマ型ファンド
- 純資産総額が少ない・減っているファンド
- 新しく設定されたばかりのファンド
- 複雑すぎるファンド
- アクティブ型の債券ファンド・レバレッジ付き債券ファンド
これらは初心者がうっかり選んでしまいがちですが、避ければ余計な損失やリスクを防ぐことができます。
初心者が選ぶべきは「低コスト&実績あり」のインデックスファンド。
- 信託報酬:0.3%以下
- 純資産総額:500億円以上(できれば1000億円以上)
- 運用実績:3年以上
- シンプルで自分でも説明できる内容
この条件を満たしていれば、長期でコツコツ続けるだけでしっかり資産を育てることができます。
「金融機関のおすすめは信用しない」
「手数料はできるだけ安く」
「わからないものには手を出さない」
このシンプルなルールを守れば、投資初心者でも大きな落とし穴を避けることができるでしょう。
投資信託選びで失敗しないために、今回のポイントをぜひ参考にしてみてくださいね。