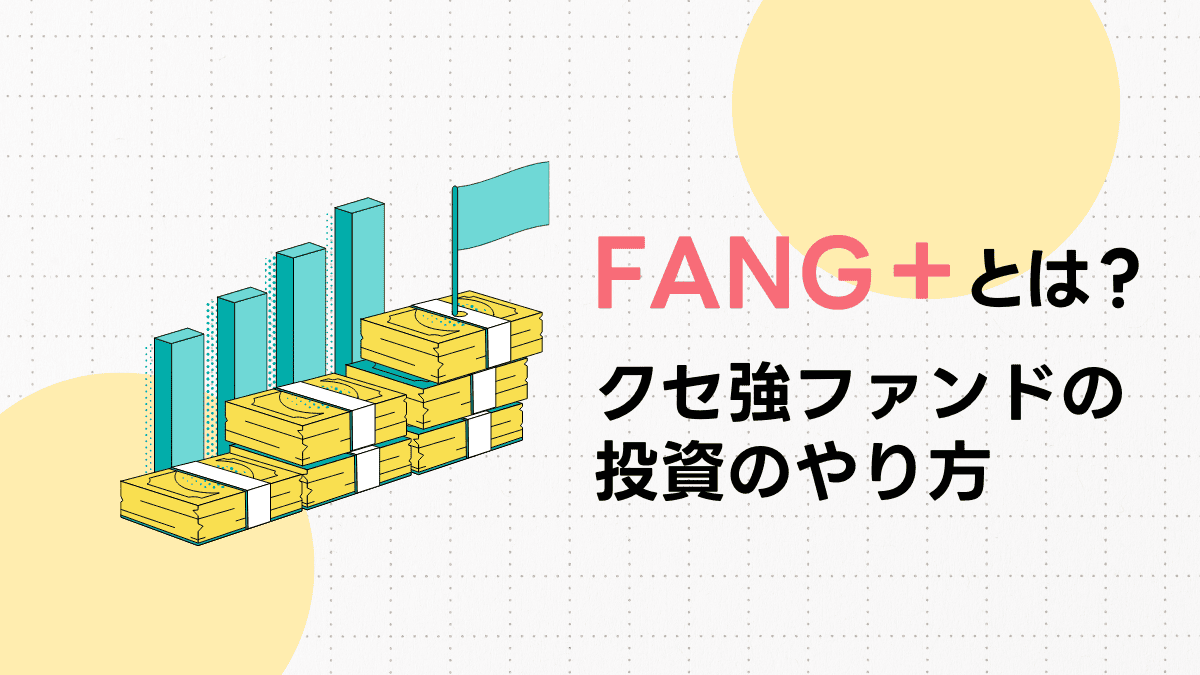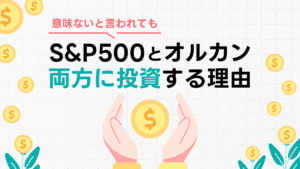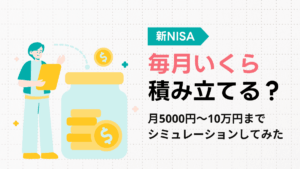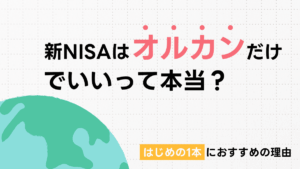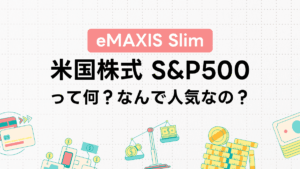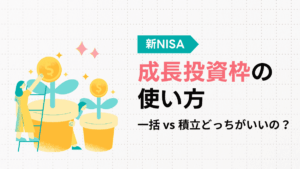FANG+(ファング・プラス)って最近よく聞くけど、実際どんな投資商品なの?
少額で積み立てても意味ある?
新NISAで選んで大丈夫なのかちょっと不安…
そんなふうに思っている方も多いのではないでしょうか。
FANG+は、米国の超有名テック企業に絞って投資できる「少数精鋭」のインデックス。
2024年には1年間で+70%の驚異的なリターンを記録し、一気に注目が集まりました。ただし、S&P500やオルカンと比べるとリスクも高く、初心者にとっては判断が難しい商品でもあります。
この記事では、FANG+の基本的な仕組みから、なぜ人気なのか、実際に積み立てる価値はあるのか、そして注意点や新NISAでの活用法まで、初めての方でもわかりやすく解説していきます。
投資初心者の方にも、すでにオルカンやS&P500に投資している中級者の方にも、きっと参考になる内容になっていますので最後までチェックしてください。
FANG+とは?── 世界を動かす“超一流テック企業”に集中投資
FANG+(ファング・プラス)は、アメリカのテクノロジー分野を代表する10社に絞って投資する「超集中型」の株価指数です。構成銘柄はいずれも、世界の経済やライフスタイルを大きく変えてきた企業ばかり。
2024年時点の構成銘柄:
- Meta(旧Facebook)
- Amazon
- Netflix
- Google(Alphabet)
- Apple
- Microsoft
- NVIDIA
- Broadcom
- CloudStrike(2024年新加入)
- ServiceNow(2024年新加入)
以前はテスラやアリババ、バイドゥといった企業も含まれていましたが、時価総額・売上成長率・財務指標などに基づいて定期的な見直しが行われていて、常に“旬”な企業で構成されているのが特徴です。
FANG+は「分散」よりも「厳選」。テクノロジーの最前線を走るリーダー企業に集中投資し、ハイリターンを狙うスタイルの指数です。
「株を1社ずつ買うのは難しいけど、ハイテク企業にまとめて投資したい」
そんな方にとって、FANG+連動型の商品は魅力的な1本となっています。
驚異のパフォーマンス実績|“たった10社”で市場を圧倒
FANG+の最大の魅力は、なんといっても圧倒的な成長力。
米国トップクラスのテック企業10社に絞ったインデックスにもかかわらず、広く分散された主要指数を大きく上回るリターンを記録しています。
7年間の積立実績|「月10万円」で約3.6倍に
たとえば、2018年1月〜2025年4月の約7年間に毎月10万円ずつ積み立てていた場合、以下のような結果になっています:
- 総積立額(元本):880万円
- 評価額:3,190万円超
- 利益:+2,310万円以上
- 年平均リターン:約30%
この成績はただのラッキーではなく、FANG+の構成銘柄がいかにこの数年で世界経済をリードしてきたかを物語っています。
10年間のリターン比較|主要インデックスとのちがい
FANG+は、S&P500やNASDAQ100といった“王道インデックス”とも比較して、驚くほどの差を見せています。
| 米国株の指数 | 過去10年の成長(目安) |
|---|---|
| S&P500 | 約5倍 |
| NASDAQ100 | 約7.8倍 |
| FANG+ | 約18倍 |
この差を見るだけでも、限られたテック企業がどれだけ爆発的な成長をしてきたかがよくわかります。
中でもNVIDIAやApple、Amazonなどは、AIやクラウドの波にうまく乗って、時価総額を何倍にもふくらませてきた代表格。まさに“世界を動かす企業たち”と言っても過言ではありません。
なんでFANG+は人気なの?その理由と3つの強み
FANG+がここまで注目されているのには、ちゃんとした理由があります。
単なる“米国株ブーム”ではなく、この10社が本当に世界をけん引している企業たちだからこそ人気が集まっているんです。
①テック分野での「圧倒的なシェア」
FANG+の企業は、それぞれの分野で圧倒的な市場シェアを持っています。
- Google(Alphabet)
検索エンジン市場で90%以上のシェア。日本でも「ググる」が日常用語になっているように、世界中で欠かせない存在になっている。
- Amazon・Microsoft・Google
クラウドサービス(IaaS)の世界シェアは、この3社だけで約66%。企業のデータ保管・サービス提供の基盤を握っている。
- Apple
iPhoneやApp Storeを通じて、世界中のモバイルユーザーのライフスタイルを変えてきた。
つまり、FANG+の企業は他に代わる企業がないほど生活やビジネスに直結するインフラのような存在になっています。
②AI・クラウド・ロボティクスなど、今後の“成長ド真ん中”にいる
FANG+は、「これからも伸びる分野」にいることも強みです。
- NVIDIA エヌビディア
AI時代の必需品「AI半導体(GPU)」のリーダー。ChatGPTのような生成AIにも使われており、今後のAI拡大とともに需要はさらに伸びると言われている。
- ServiceNow サービスナウ
業務の自動化プラットフォームを提供。大企業の社内業務効率化に導入されるケースが増えている。
- CloudStrike クラウドストライク
AIを活用した次世代型セキュリティ企業。サイバー攻撃が高度化する中で、注目度が急上昇している。
FANG+に含まれる企業の多くは、AI・クラウド・セキュリティ・ロボティクスなど、これから10年、20年と成長が期待されるテーマにど真ん中で関わっているんです。
③銘柄の“新陳代謝”が活発で時代に合わせて進化する
FANG+は、固定された10社ではありません。
成長が鈍化した企業は外され、将来有望な新しい企業が加わるという“新陳代謝”が活発な指数です。
実際、以下のような入れ替えが行われてきました。
- 2021年:Twitterが除外、Microsoftが新規加入
- 2022年:アリババ・バイドゥが除外、AMD・Snowflakeが加入
- 2023年:AMDが除外、Broadcomが加入
- 2024年:Tesla・Snowflakeが除外、CloudStrike・ServiceNowが加入
つまり、FANG+は「成長企業を選び直してくれる投資信託」ともいえます。
過去の実績にすがるのではなく、未来に強そうな企業へ定期的に入れ替えることで、投資対象としての鮮度を保っているのです。
これら3つの強みを兼ね備えているからこそ、FANG+は投資家から高い評価を受けており、「少額でもいいから持っておきたい!」という声が多いのです。
FANG+のリスクと注意点
FANG+は、驚異的な成長を遂げてきた注目ファンドですが、その裏側には、「リターンが大きい=値動きも大きい」というハイリスクの特性があることも忘れてはいけません。
好調な年には+100%を超えることもありますが、不調な年はマイナス30〜50%の暴落も起こり得ます。
実際の例:
- 2020年:+83%
- 2021年:+31%
- 2022年:-33% ←大幅な調整
- 2023年:+115%
- 2024年:+70%(想定)
このように、良い年と悪い年の差が極端に大きいのがFANG+の特徴。
資産が短期間で2倍にも3倍にもなる一方で、同じくらいのスピードで半分になることもあると理解しておく必要があります。
銘柄が10社だけ=分散リスクが弱い
FANG+は、たった10社に集中投資しているという点には注意が必要です。
| 投資対象 | |
|---|---|
| オルカン | 世界47カ国・約3000社 |
| S&P500 | 米国の代表企業500社 |
| FANG+ | テック系10社のみ |
たった1〜2社に問題が起きるだけで、指数全体が大きく揺さぶられるリスクがあります。
テーマ特化型ならではのリスク
FANG+は、IT・AI・クラウド・自動化といった「テクノロジー特化型」のファンド。
トレンドに乗ったときの伸びは強烈ですが、同じテーマの逆風が吹くと一気に崩れます。
たとえば、以下は指数が大きく下がる原因となり得ます。
- 金利上昇
- AI規制・反トラスト法(独占禁止法)
- 技術の陳腐化や競合の登場
①金利上昇リスク
FANG+に含まれる企業は「グロース株(成長株)」と呼ばれるタイプの銘柄で、売上よりも「将来もっと成長するはず!」という期待で買われている株です。
このタイプは、金利が上がると株価が下がりやすいという性質があります。
2022年にはアメリカの中央銀行(FRB)が急激な利上げを行い、FANG+は1年で約−33%も下落しました。
これは、金利上昇が成長株にとっては逆風になることを表した典型例です。
②AI規制・反トラスト法(独占禁止法)
FANG+の企業は、AIやデジタル技術を武器に、私たちの暮らしや社会を大きく変えるようなサービスを次々に生み出しています。
でもその一方で、「このまま好き放題やらせていいのか?」という疑問の声が世界中で高まってきているのも事実。
各国の政府や国際機関は、規制の整備に本腰を入れ始めました。
EU(ヨーロッパ)ではAIが人間の権利や安全に悪影響を与えないよう「AI法案」の導入を、アメリカではGoogleやAmazonなどの巨大企業に対して、独占禁止法(反トラスト法)の調査を進めています。
FANG+に含まれる企業は、データや技術に強く依存して収益を得ているため、規制が入ると一気にビジネスモデルが揺らぐ可能性があります。
③ 技術の陳腐化や競合の登場
テクノロジーの世界は変化が非常に速く、「数年後には別の企業が主役になっていた」ということもよくあります。
たとえば、
- ChatGPTで注目されたOpenAI → ほぼ無名から業界の中心に
- Facebook(Meta)も、TikTokの登場で若者の利用が激減
- 過去の王者Intelは、半導体の競争でNVIDIAに後れを取って株価が低迷
FANG+の企業が今は最強でも、「10年後も同じメンバーが活躍している保証はない」というのが最大の不確実性です。
地政学リスクも無視できない
FANG+の多くの企業はグローバルで展開しているため、世界情勢の変化にも敏感です。
- 米中対立、台湾有事などによる半導体供給の不安
→ 米国の制裁、輸出規制により、半導体・AI分野の成長が抑制される可能性
- 欧州や中国での規制強化による収益悪化
→ 世界の先端半導体の90%以上は台湾TSMCが製造。もし供給が止まれば、NVIDIA・Appleなどの業績に直結します
- 為替の影響(円高でパフォーマンスが落ちる可能性)
→ 投資は円建てでも、企業の収益はドル建て。円高が進むと、日本の投資家にとってのパフォーマンスが目減りします
といった予測不能な“外的ショック”もリスク要因です。
FANG+の将来性|10年後も勝ち続ける?
FANG+の10社は今から10年前、2015年の時点でもすでに世界的に有名な存在でした。
たとえば…
- AppleはiPhoneでスマホ市場をリード
- Amazonはネット通販で世界を席巻
- Google(Alphabet)は検索と広告でトップ
- Meta(旧Facebook)はSNSの先駆け
そしてこれまでの10年間、まさにIT業界の最前線をけん引してきました。
今、これらの企業はただ現状維持するのではなく、AI・複合現実・ロボティクスなどの「次の技術」に本気で取り組んでいます。
成長のカギは、拡大し続ける「AI市場」
FANG+の将来性を語るうえで欠かせないのが、AI(人工知能)の市場がこれから爆発的に伸びていくという予測です。
ChatGPTのような生成AIはもちろん、医療・金融・製造などあらゆる分野でAIの活用が加速しており、世界のAI市場は2023年から2032年にかけて約6倍に成長すると言われています。
FANG+の10社は、AIの基盤・応用・ハードウェア・サービスのすべてに関わっているのが強み。
- NVIDIA:AIを動かすための“脳”であるGPUを供給
- Amazon:クラウドでAIを動かす“土台”を提供
- AppleやMeta:AI体験をユーザーに届ける“デバイスと空間”を構築
これから社会全体がAIに支えられていく中で、その中核となる仕組みやサービスを提供する側の企業なのです。
もちろん未来は予測通りにはいかないこともありますが、FANG+は、「これからの時代をリードする企業にまとめて投資できる」将来性のある投資先といえるでしょう。
新NISAでFANG+をどう活用する?
FANG+に投資するには大きく分けて2つの方法があります。
- FANG+のインデックスファンド(投資信託)を積み立て投資する
- FANG+のETF(上場投資信託)を自分のタイミングで買う
どちらも投資信託ですが、購入できる場所や買い方、コストなどさまざまな違いがあります。
投資信託とETFのちがい
| 通常の投資信託 | ETF(上場投資信託) | |
|---|---|---|
| 売買のタイミング | 1日1回 (基準価額で売買) | リアルタイム売買が可能 |
| 購入場所 | 証券会社・銀行など | 証券会社のみ |
| 最低購入額 | 100円から | 1口単位 (数千円~数万円) |
| 取引コスト | 基本的に売買手数料なし 信託報酬のみ | 売買手数料+信託報酬 |
| 積立投資 | クレカ対応の証券会社も多数 | クレカ積立不可 |
| 自動再投資 | 再投資される商品あり | 基本なし |
| NISA つみたて投資枠 | 商品による | |
| NISA 成長投資枠 |
FANG+の投資信託・ETFを使った投資についてそれぞれ見ていきましょう。
①つみたて投資枠でほったらかし投資するなら投資信託
NISAで手軽に投資するなら、FANG+の投資信託をつみたて投資枠で購入する方法がよいでしょう。
銘柄は「iFreeNEXT FANG+ インデックス」です。
一度設定すれば自動で買い付けしてくれるので、「手軽にFANG+を取り入れたい」「まずは少額で始めたい」という方に向いています。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.7755% |
| 新NISA「つみたて投資枠」対応 | 毎月一定額を自動で積立可能 |
| 100円から始められる | 少額から投資が可能なので、初心者でも気軽にチャレンジできる |
| クレジットカード積立もOK | 楽天証券やSBI証券などでクレカ積立に対応 |
| 価格は1日1回(基準価額)で決定 | リアルタイム売買はできないが、ほったらかし投資に向いている |
こんな人は投資信託が◎
- 初心者・投資を始めたばかりの人
- クレジットカード積立を活用して、ポイントもお得に貯めたい人
- 手間をかけずに長期運用したい人
つみたて投資枠を利用してコツコツ積み立てしたい人、ほったらかし投資をしたい人は投資信託がおすすめ!
②狙ったタイミングで買いたいならETF
ETFを使えば、株式と同じようにリアルタイムで取引できます。
銘柄は「iFreeETF FANG+(ETF)」。
市場が開いている時間はいつでも購入できるので、「FANG+が10%下がったら買う」など、ルールを決めた“タイミング投資”にも活用できます。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 信託報酬 | 年0.605%(税込) |
| リアルタイム売買が可能 | 株式同様、日本市場(9:00~15:00)で価格を見ながら売買できる |
| 新NISA「成長投資枠」対応 | つみたて投資枠では購入不可、成長投資枠のみ |
| 最低購入単位:1口単位 | 数千円から購入可能、クレカ積立は不可 |
| 分配あり(年2回:6月・12月) | 分配金はありますが、再投資した上昇率では非課税扱い 。 |
こんな人はETFが◎
- 値下がりしたタイミングで「狙って買いたい」人
- コストをできるだけ抑えたい人
- ETFや株式の売買に慣れている中級者以上
ETFは中級者向きのため、いくつか注意点やデメリットがあります。
- 株式と同じように“取引の手間”がある
→ 売買のタイミングを自分で判断する必要があり、放置しておくスタイルにはやや不向き。
- 少額からの積立に向いていない
→ 毎月コツコツ積立したい人には不向き。クレジットカード積立や100円単位での購入もできません。
- 買値と売値に差(スプレッド)がある
→ 市場で売買するため、タイミングによっては実質コスト(売買の差)が大きくなることがあります。
運用コストを少しでも抑えたい人や、株価が下がったときに買い増ししたい人、自分でタイミングを見ながら投資したい人はETFがおすすめ!
FANG+でサテライト投資するならどう買う?
サテライト投資とは、ポートフォリオの中で「全体のごく一部を使って、リターンを狙う攻めの投資をする」戦略です。
- メイン(コア):長期・安定・低リスク運用
例)S&P500、全世界株式(オルカン)など
- サブ(サテライト):短中期・高成長狙い・高リスク運用
例)FANG+、SOX(半導体)、新興国株、レバレッジ型など
ざっくり言えば、「本体は守り重視、端っこで夢を追う」のがサテライト投資です。
FANG+はたった10社のテック株に集中しているため、上下の値動きがとても激しいです。
単体で持つとリスクが高すぎるため、コア資産(守り)とセットにするのが鉄則!
おすすめの組み合わせ例はこちら。
| 組み合わせ | 割合 | |
|---|---|---|
| オルカン・FANG+ | 9:1〜8:2 | 世界全体+テック成長狙いの王道構成 |
| S&P500・FANG+ | 8:2 | 米国+ハイテクへの集中で成長を追う |
| 債券・FANG+ | 7:3 | 価格変動リスクを抑えたい人向け |
| 現金多め・FANG+ | 9:1 | 投資が初めての人向けの慎重スタート |
FANG+はあくまでおまけ。主力ではないと割り切ることが大事です!
FANG+を使ったサテライト投資は、欲張らず淡々と行いましょう
「見ない勇気」が必要な投資
FANG+は1日で数%上下することも珍しくなく、1週間で資産が大きく増えたり減ったりすることもあります。
- 「今月プラス10万円だったのに、翌週にはマイナス8万円…」
- 「せっかく増えたのに、一瞬で元通り…」
こんな波を毎日のように見ると、不安になったり焦って売ってしまったり…精神的に振り回されてしまう方も多いです。
だからこそ、「見すぎない」のが大事。
- 少額で始める
- 毎月コツコツ積み立てる
- 値動きをいちいち気にしない
といった“マイルール”を作るのがポイントです。
「証券口座は月1回だけチェックする」など、自分が冷静でいられる距離感を保ちましょう。
まとめ:FANG+は”未来の成長”に乗っかる投資先
これからの時代をリードする「アメリカの超有名テック企業10社」にギュッと絞って投資するFANG+。
2024年には+70%という驚きのリターンをたたき出し、多くの投資家が注目しています。
「少数精鋭」だからこそ伸びしろも大きく、AI・クラウド・自動化・セキュリティといった成長分野のど真ん中に投資できるのがいちばんの魅力。
成長のスピードが早いぶん値動きも大きく、1週間で大きく増えたり減ったり…ということも珍しくないので、メインではなく、サブとして少し取り入れる「サテライト投資」がおすすめです。
- オルカンやS&P500をメインにしつつ、FANG+は月5000円だけ積立
- 値下がりしたタイミングでETFを1万円分だけ買ってみる
- 投資総額の1〜2割にとどめて「夢枠」として楽しむ
FANG+は、テクノロジーの最先端を走る企業に少額から投資できるので、新NISAを使いながら自分のペースで“未来への投資”を楽しんでみてくださいね。